 ぼくとこの映画は同い年である。4年に一度しか巡ってこない2月29日、ベルナルド・ベルトルッチ監督の「暗殺の森」のリバイバル上映がロンドンの一部の映画館で始まった。その映画館というのがバービカン、ルノワール、BFIサウスバンク、エヴリマンで、まさにぼくが一番良く脚を運んでいる<個人的に思い入れの深い映画館トップ4>での公開である。大統領選もオリンピックも遠い世界にもたらされた閏年の実感がベルトルッチだなんてちょっとうれしい。ベルトルッチ作品はご他聞にもれず「ラストエンペラー」が初めてだったのだが、その後「シェルタリング・スカイ」、「ラスト・タンゴ・イン・パリ」、そして幸運にも一瞬だけ上映された5時間の大作「1900年」と立て続けに観る機会に恵まれた。すっかりベルトルッチのファンになってしまったわけだが、一番打ちのめされたのはこの「暗殺の森」である。こういった古い文芸作品っぽい映画のリバイバル上映は、東京のそれよりもロンドンの方が頻度、質ともに上の感があるが、「暗殺の森」は来るたびに必ず観にいっている映画の1つである。
ぼくとこの映画は同い年である。4年に一度しか巡ってこない2月29日、ベルナルド・ベルトルッチ監督の「暗殺の森」のリバイバル上映がロンドンの一部の映画館で始まった。その映画館というのがバービカン、ルノワール、BFIサウスバンク、エヴリマンで、まさにぼくが一番良く脚を運んでいる<個人的に思い入れの深い映画館トップ4>での公開である。大統領選もオリンピックも遠い世界にもたらされた閏年の実感がベルトルッチだなんてちょっとうれしい。ベルトルッチ作品はご他聞にもれず「ラストエンペラー」が初めてだったのだが、その後「シェルタリング・スカイ」、「ラスト・タンゴ・イン・パリ」、そして幸運にも一瞬だけ上映された5時間の大作「1900年」と立て続けに観る機会に恵まれた。すっかりベルトルッチのファンになってしまったわけだが、一番打ちのめされたのはこの「暗殺の森」である。こういった古い文芸作品っぽい映画のリバイバル上映は、東京のそれよりもロンドンの方が頻度、質ともに上の感があるが、「暗殺の森」は来るたびに必ず観にいっている映画の1つである。
それにしても、「ラストエンペラー」もさることながら、「暗殺の森」日本版のDVD、やばいことになってますね、しかし。あと、いまだにべルトリッチって表記する人が少なくないようで、それってちょっと興味深い現象だと思う。長年の癖はダイハードなのだろうか?
2008年2月29日金曜日
閏年の実感が運んできたもの
2008年2月28日木曜日
黄昏のブリストル
 自分では覚えていないのだが、叔父の述懐するところによれば、ぼくは4歳のときに識別できるクルマが既に数百台はあったそうである。環境問題は気になることだけど、クルマって、やっぱり好きなのよね。で、ハイゲートに散歩に行ったときに見かけた程度のいいブリストル。おそらく411だろう。410との違いはステアリングを見れば分るのだが、チェックするのをすっかり忘れていた。各モデルごとに数十台しか作られないブリストル。歴史は1910年に遡り、今でも生産を続けているブリストル。リアム・ギャラガーは性格悪いし歌も上手くないけど、乗ってるクルマはブリストルだ。新車のブリストルは、あんまり興味ないんだけどね。
自分では覚えていないのだが、叔父の述懐するところによれば、ぼくは4歳のときに識別できるクルマが既に数百台はあったそうである。環境問題は気になることだけど、クルマって、やっぱり好きなのよね。で、ハイゲートに散歩に行ったときに見かけた程度のいいブリストル。おそらく411だろう。410との違いはステアリングを見れば分るのだが、チェックするのをすっかり忘れていた。各モデルごとに数十台しか作られないブリストル。歴史は1910年に遡り、今でも生産を続けているブリストル。リアム・ギャラガーは性格悪いし歌も上手くないけど、乗ってるクルマはブリストルだ。新車のブリストルは、あんまり興味ないんだけどね。
2008年2月27日水曜日
枠から外れるために
 ぼくが興味を持っていることを、すごく的確に知っている友だちがくれた本に「Off the Grid: Modern Homes and Alternative Energy」というのがある。英語でOff-the-gridあるいはOff-gridというのは、「電気、ガスの類いを供給会社に頼らない」、みたいなことを意味する。この本には、アメリカ国内で実践されている様々な形の自活型の建物が紹介されている。広野のど真ん中、風力および太陽発電による大型の一軒家から、マンハッタンにあって電力会社から電気の供給を受けていないという「どうやったらそんなことが可能に?」みたいな5階建てまで、色々出ていて面白い。
ぼくが興味を持っていることを、すごく的確に知っている友だちがくれた本に「Off the Grid: Modern Homes and Alternative Energy」というのがある。英語でOff-the-gridあるいはOff-gridというのは、「電気、ガスの類いを供給会社に頼らない」、みたいなことを意味する。この本には、アメリカ国内で実践されている様々な形の自活型の建物が紹介されている。広野のど真ん中、風力および太陽発電による大型の一軒家から、マンハッタンにあって電力会社から電気の供給を受けていないという「どうやったらそんなことが可能に?」みたいな5階建てまで、色々出ていて面白い。
たったの3日間ではあるが、アールズコートでECOBUILDという催しが始まり、明日までの開催だそうである。ゼロ・カーボンハウスだとか、ソーラー・シティだとか、目新しいものでもなさそうだけど、そういうわけでここら辺は長いこと興味のある分野なので、ぜひ現地で確認してみたいと思う。500以上団体による主催、2万人の動員を見込んでいるそうである。行けるかなー。
2008年2月26日火曜日
ピカデリー、甘いもの数百メートル

個人的にはマカロンはラデュレよりもPaulよりもピエール・エルメのほうが好きだ。ナゼかは分らないが、エルメはパリと東京にしかお店がない。でもときどき食べたいマカロンや、ほとんどいつでも食べたい和菓子とチョコが、ピカデリーにはすべてある。それも、全力疾走なら10秒以内みたいな距離に。あまつさえ、お向かいにはフォートナム&メイソン、Patisserie Valerieも目と鼻の先だ。危険である。今日のお買い物はブリュワー・ストリート、駅を出て、間違っても左に出てはならない。
2008年2月25日月曜日
平凡にして活躍せる文字
 いつも思うのだが、ジェイン・オースティン作品の最大の敵はそのタイトルではないだろうか。恋愛小説やビルトゥンクスロマンへの理解があるとか、「大学の専攻は英文学です」とかなら別だろうけども、長編第一作となる「分別と多感」といい、何度も映像化されている「高慢と偏見」(「自負と偏見」の邦訳もある)といい、ちょっとタイトルから<読んでみようかな>と思わせるにはほど遠いものがあるように思う。かく言うぼくも映画化、テレビ化されて「観た」オースティンのほうが、「読んだ」オースティンよりも多い。オースティンは多作ではないので、映像化された作品はそれぞれ何バージョンもあるというのが、その理由のひとつではあるのだが。ところで、ぼくが初めてBBC版「高慢と偏見」をテレビで観たのは95年だが、正直半分も分らなかった。当時の中流および上流階級の話し振りがそうだから、ということではあるのだが、おそろしく回りくどい(字幕で訳されているのはおそらく全体の4分の1未満程度じゃないだろうか)。英国内の本放送で観ていたので当然だが、字幕はない。95年といえばぼくはロンドンに来てまだ2年目だった。なんとなく面白そうかなという感触はあったので、原作を読んで話の筋を掴んでみたいと思ったのだが、おそらく当時の英語力で読んでもまったく分らなかったろうと思う。2003年頃になって初めて読む勇気が出たのだが、BBC版を観ていたので掴みやすかった。逆に、テレビ版に吊られすぎないように読もうと意識したくらいだ。読んでみて、エリザベスは美形ではないが芯の強い女性として描かれているというのが分ったし、ダーシーはコリン・ファースとは似ても似つかない人物だというのも分った。ちなみに、映画版の「プライドと偏見」を撮ったジョウ・ライトは、原作を読まずに監督したそうである。面白い試みだと思う。でもエリザベスは美人ではないし、ダーシーはあんなに激しくカリスマ性がバイパスされた俳優が演じては決してならない。
いつも思うのだが、ジェイン・オースティン作品の最大の敵はそのタイトルではないだろうか。恋愛小説やビルトゥンクスロマンへの理解があるとか、「大学の専攻は英文学です」とかなら別だろうけども、長編第一作となる「分別と多感」といい、何度も映像化されている「高慢と偏見」(「自負と偏見」の邦訳もある)といい、ちょっとタイトルから<読んでみようかな>と思わせるにはほど遠いものがあるように思う。かく言うぼくも映画化、テレビ化されて「観た」オースティンのほうが、「読んだ」オースティンよりも多い。オースティンは多作ではないので、映像化された作品はそれぞれ何バージョンもあるというのが、その理由のひとつではあるのだが。ところで、ぼくが初めてBBC版「高慢と偏見」をテレビで観たのは95年だが、正直半分も分らなかった。当時の中流および上流階級の話し振りがそうだから、ということではあるのだが、おそろしく回りくどい(字幕で訳されているのはおそらく全体の4分の1未満程度じゃないだろうか)。英国内の本放送で観ていたので当然だが、字幕はない。95年といえばぼくはロンドンに来てまだ2年目だった。なんとなく面白そうかなという感触はあったので、原作を読んで話の筋を掴んでみたいと思ったのだが、おそらく当時の英語力で読んでもまったく分らなかったろうと思う。2003年頃になって初めて読む勇気が出たのだが、BBC版を観ていたので掴みやすかった。逆に、テレビ版に吊られすぎないように読もうと意識したくらいだ。読んでみて、エリザベスは美形ではないが芯の強い女性として描かれているというのが分ったし、ダーシーはコリン・ファースとは似ても似つかない人物だというのも分った。ちなみに、映画版の「プライドと偏見」を撮ったジョウ・ライトは、原作を読まずに監督したそうである。面白い試みだと思う。でもエリザベスは美人ではないし、ダーシーはあんなに激しくカリスマ性がバイパスされた俳優が演じては決してならない。
映画化されたオースティンということで行くと、ぼくはアン・リーのファンだし、エマ・トンプソンが5年かけて脚本を書いたという「いつか晴れた日に」は好きな映画の1つである。そりゃまあ、トンプソンの泣きはギャグだとか、「ちょっとケイト・ウィンスレットの2歳上には見えないんじゃないかい?」とかはあるにせよ、何をやっても秀逸のイメルダ・ストーントンやアラン・リックマンなど含め、映画そのものの出来はすごくいいと思う。それに、「なんで?」という邦題かもしれないが、「分別と多感」よりも取っ付きやすいし、雰囲気を的確に伝えている名訳じゃないだろうか。2008年のBBC<新春ドラマスペシャル>にもジェイン・オースティンがあったのだが、これが「分別と多感」だった。はっきり言って、映画版の数百倍はいいと思う。といった感じでせっかくなのでと、改めて読んでみようと思い立ったのがこの「分別と多感」の原作である。ペンギンから出ている文字もくっきりして読みやすい活版のペーパーバックを仕入れてみた。本日、読了。
200年前の英語なので、文法とか用法とかは現代英語と若干違うのだが、すごく分りやすい。やはり人物の描き方は卓越だと思う。年齢にしては若干老成した感のあるエレナ(Elinorは、エリノアとかエリナとかが一般的のようだけど、音的には「エレナ」だと思う)といい、マリアンの<成長への痛い階段>といい。一見好青年なのだが後に本性を現す下り、えげつない人物はもう本当にかなりえげつなく描かれていたり。話の筋っていうことだと、ぶっちゃっけ「高慢と偏見」とかなり同じ話の展開である。小津安二郎の「晩春」と「秋刀魚の味」くらい同じ話だと思う。が、何が起こるか分ってるのに「この後どうなるんだろう?」と読むたびに思わせられる。大した事件が起こらないのにページを繰らずにはいられないというすごさが、オースティンにはある。漱石の言った、オースティンは「写実の泰斗なり。平凡にして活躍せる文字を草して技神に入る」というのも、全くその通りだと思う。
ところで、おそらく日本ではMr.ビーンとしてのほうが有名であろうロウワン・アトキンソンの最高傑作、コメディ「ブラックアダー」の第3シリーズのエピソード名はすべて「分別と多感(原題はSense and Sensibility)」のパロディである。Dish and Dishonestyだとか、エピソード3なんてNob and Nobilityだ。訳すとおもしろさが伝わらないので敢えて訳さないが、これの意味が分かっちゃった人は今すぐ職員室に出頭してください。
2008年2月24日日曜日
スペイン料理大会
 スペイン人とのハーフで、かつてはシェフもやっていた友だち。ドックランズというかつては倉庫街、今はトレンディなウォーターフロント、みたいなところにロフト付きのマンションを持っている。日曜なので、やつの手づくりでスペイン料理三昧である。クリームチーズとチョリソ、マッシュルームにチャイブが乗っているタパスだとか種々雑多なオリーブなどから始まって、チキンとピーマンのトマト煮のメインにマンチェゴとメンブリヨというかなりスペイン尽くしの午後。
スペイン人とのハーフで、かつてはシェフもやっていた友だち。ドックランズというかつては倉庫街、今はトレンディなウォーターフロント、みたいなところにロフト付きのマンションを持っている。日曜なので、やつの手づくりでスペイン料理三昧である。クリームチーズとチョリソ、マッシュルームにチャイブが乗っているタパスだとか種々雑多なオリーブなどから始まって、チキンとピーマンのトマト煮のメインにマンチェゴとメンブリヨというかなりスペイン尽くしの午後。
そんな感じで、たまにやってる<誰かの家で手料理>な午後の集い、香港セレブによるヤバい写真流出事件から、果ては春画の話まで、オトナの午後はゆっくり朗らかに進む。午後の遅めの時間に降り始めた雨が、ほぼ真横を通るDLRの線路を鳴らす。ドームは青くライトアップされている。セミフレードが出てくる頃には料理のどこかに入っていたんであろう微量のアルコールが、ぼくの頭も回し始める。「今日はありがとね」SMSを帰りのクルマの中から打ったのだが、その返事によればぼくを除いた9人でリヨハを13本空けたらしい。主催の二人がかなりの酒豪だからねえ。
2008年2月23日土曜日
空気で走るクルマ
 BBCの記事を見たのは先週なのだが、どうやらそんなに目新しいことでもないらしいことが、ちょっと調べると分ってくる。なんのことかと言うと、空気で動くクルマのことである。空気で動くだなんて、なんてエコなんだろう。燃料電池だとか水素エンジンよりも利便性も高そうだ。「これって、もしかして最新?」というのがすぐに思ったことだが、空気のクルマはけっこう昔からあるらしい。それも、十年だとかそういうレベルの過去ではない。聞けば、300年以上前にその原理は記録されているんだそうだ。蒸気機関の発明者としても知られるドニ・パパンという人が1687年に時の国王チャールズ2世の擁護の下、ロンドンでこれを考案している。
BBCの記事を見たのは先週なのだが、どうやらそんなに目新しいことでもないらしいことが、ちょっと調べると分ってくる。なんのことかと言うと、空気で動くクルマのことである。空気で動くだなんて、なんてエコなんだろう。燃料電池だとか水素エンジンよりも利便性も高そうだ。「これって、もしかして最新?」というのがすぐに思ったことだが、空気のクルマはけっこう昔からあるらしい。それも、十年だとかそういうレベルの過去ではない。聞けば、300年以上前にその原理は記録されているんだそうだ。蒸気機関の発明者としても知られるドニ・パパンという人が1687年に時の国王チャールズ2世の擁護の下、ロンドンでこれを考案している。
それって、かなりすごいんじゃないだろうか。ガソリンよりもディーゼルよりも前に、空気のクルマが発明されていたのだ。それが、300年たってついに実用化、インドのタタが今年中に発売に踏み切るそうだ。燃費も良くて、軽量、クルマ自体も高くない。いいこと尽くめのようだが、実際のところはそうでもない。タンクを始め、ボディは接着のグラスファイバーである。つまり、リサイクルはどうよ?ということである。そうは言っても、これはかなり楽しみな展開である。それにしても、もう少しデザインが良ければねえ。
2008年2月22日金曜日
斜陽、国際駅ターミナル
 ぼくと同じことを考える人は多いようである。いや、ぼくが誰でも考えるようなことを着想しただけだな。かつて、ドーバー海峡を越えパリへとつながる国際鉄道ユーロスターの発着駅だったウォータールー国際駅のその後を見届けようと、出かけてみたわけである。
ぼくと同じことを考える人は多いようである。いや、ぼくが誰でも考えるようなことを着想しただけだな。かつて、ドーバー海峡を越えパリへとつながる国際鉄道ユーロスターの発着駅だったウォータールー国際駅のその後を見届けようと、出かけてみたわけである。
カムデンにあるMTVビル、スーパー「セインズベリ」などでも知られるニコラス・グリムショーの建築設計。この建築は、天井は低いが幅もなく奥行きの長いカーブした敷地という制約を、空間においても構造デザインにおいても無理なく自然に利用していた。 11月にユーロスターの発着駅がセント・パンクラスに移り、その後どうなったのか気になっていたのだが、見事なまでに「丁重に放置」されていた。ちょっと悲しげ。ここからパリに向かった81,891,738人の一人だった者としても、取り壊しには、ならないで欲しいと思う。
2008年2月21日木曜日
悲劇としての機械、写真、性
 今日から始まったテイト・モダンの「Duchamp, Man Ray, Picabia」。ぼくにとっては、ヒーロー勢揃いである。この3人が一堂に介するだなんて、考えただけでもワクワクする。今回の展示はレベル4になんと13室、182点に及ぶ3人の作品を一挙公開なのだ。まさに、千載一遇のチャンスである。この機会を逃したら、これだけの規模でこのコンセプチュアルアートのゴッドファーザーたちを一気に見られることは二度とあるまい。レイヨグラフ、デュシャンの「遺作」、チェス、過去四半世紀というもの、この3人はぼくを憑依し続けてきたのだ。
今日から始まったテイト・モダンの「Duchamp, Man Ray, Picabia」。ぼくにとっては、ヒーロー勢揃いである。この3人が一堂に介するだなんて、考えただけでもワクワクする。今回の展示はレベル4になんと13室、182点に及ぶ3人の作品を一挙公開なのだ。まさに、千載一遇のチャンスである。この機会を逃したら、これだけの規模でこのコンセプチュアルアートのゴッドファーザーたちを一気に見られることは二度とあるまい。レイヨグラフ、デュシャンの「遺作」、チェス、過去四半世紀というもの、この3人はぼくを憑依し続けてきたのだ。
この3人に共通するのは、悲劇的な要素だと思う。思えば、テイト・モダンがオープンしたときにレストアされたもののひとつがマルセル・デュシャンの「泉」だった。ヒビの入ったデュシャンの「泉」を丹念に修復していく映像は、今でも記憶に残っている。1917年に、アイディアに行き詰まった芸術家によって署名されただけの小便器。テイト・モダンにあるのは1964年のレプリカだが、最新技術を使って「新品同様」にするわけである。リチャード・ハミルトンとの合同による「大ガラス」のレプリカもそうだが、これって、ちょっと悲しい光景かもしれない。しかし、悲劇というのは、現代芸術につきものなのかもしれないとも思う。否、シャトー・ラトゥールを料理に使ったり、晩年は作品を作るよりチェスに興じていたデュシャンの後半生は悲劇などではない。
芸術が、永久に塗り替えられた瞬間。見たことのない作品も相当数集められている。2008年5月26日まで開催。
2008年2月20日水曜日
和洋折衷自家製味噌の仕込み顛末
 今日はBRIT賞というイギリスのポップ音楽賞の授賞式があるが、そんなことより個人的には味噌の仕込みである(Take Thatって言われても、音楽聞いたことないし)。さて、味噌を手づくりするのは今回が2回目。姉から有機原料を使用した「乾燥こうじ」なるものを送ってもらい、初めて味噌を仕込んでみたのが2007年3月。今年も同じ麹を送ってくれたのでさっそく、というわけである。大豆は、イギリスで売られているものはほぼ100%そうなのだが、アメリカ産である。麹も有機だし、せっかくなので有機大豆にしてみた。去年の味噌に使った塩は、普段の料理に使っているモルドン塩というイギリス南東部の海岸で製造されている「塩っからくない」結晶のお塩だった(モルドンは日本でも売ってるけど、お値段的にちょっと高級品になってしまう)。といった感じで「お味噌'07」、出来はというと、モルドン塩は粗塩などと違って比重は軽いこともあったせいか、カビがすごくて麹のお米のカタチも残っていて、「来年への課題」が色々残ったものだった。お味としては、甘めで好みのものではあったものの。
今日はBRIT賞というイギリスのポップ音楽賞の授賞式があるが、そんなことより個人的には味噌の仕込みである(Take Thatって言われても、音楽聞いたことないし)。さて、味噌を手づくりするのは今回が2回目。姉から有機原料を使用した「乾燥こうじ」なるものを送ってもらい、初めて味噌を仕込んでみたのが2007年3月。今年も同じ麹を送ってくれたのでさっそく、というわけである。大豆は、イギリスで売られているものはほぼ100%そうなのだが、アメリカ産である。麹も有機だし、せっかくなので有機大豆にしてみた。去年の味噌に使った塩は、普段の料理に使っているモルドン塩というイギリス南東部の海岸で製造されている「塩っからくない」結晶のお塩だった(モルドンは日本でも売ってるけど、お値段的にちょっと高級品になってしまう)。といった感じで「お味噌'07」、出来はというと、モルドン塩は粗塩などと違って比重は軽いこともあったせいか、カビがすごくて麹のお米のカタチも残っていて、「来年への課題」が色々残ったものだった。お味としては、甘めで好みのものではあったものの。
さあて、というわけで今年はお塩も海塩にして、豆も麹もマッシャーで丹念につぶして、と。
フードプロセッサーでもいいのだろうが、なんとなく電動のものは使わないで仕込みたいかな、程度の理由でマッシャーである。あと、これはまったく偶然なのだが、今週母が送ってくれた古い日本の雑誌の中に、味噌の作り方が出ていた。これによると、塩を麹に混ぜ、潰した大豆に種味噌として去年の味噌を少し混ぜる、とある。なるほどね。ヨーグルトも少しとっておいたやつに牛乳足すと、自家製ヨーグルトになるもんね。「じゃあ」ということで、これまた姉が送ってくれた甘口のお味噌に、種味噌として参加してもらった(このお味噌、本当においしかったので、足す前にかなり逡巡したのだが)。ちなみに容れ物は、味噌瓶は持ってないのでパイレックスとキャセロールである。イギリスでは消毒用アルコールが手に入りにくい。チャツネを作るときと同じ要領でオーブンを75度にセット、30分ほど焼いて消毒したものをベルモットでサッと拭く。
ところでイギリスで売られている豆は小豆や大正金時やガルバンゾなど、大体どんな豆でもそうなのだが、国産のものと違って火の通りにムラがある。今回のアメリカ産大豆も一日半浸しておいた上、半日かけて煮たのだがばっちり「親指と小指でつぶせる」ものが8割、「ん〜、程よい歯応え」なカタさのもの2割、みたいな出来だった。
たとえば、お醤油を一般家庭で醸造するのはハードルが高いが、<普通は買ってくるけど、家で作っても簡単でおいしいもの>の中に、餃子の皮と味噌があるように思う。「え?こんなに簡単だったの?」という簡単さだし。それに巷間言われる<努力のかい>が、必ずあるものだとも思う。「冬にはいつもすること」みたいな恒例行事にしたいと思った味噌作り。5月の下旬には食べられるものになっているはずである。
2008年2月19日火曜日
キワモノ揃いの一日
 敢えてしようと思ってのことでは決してないのだが、今日はいろんなジャンルのゲテモノが揃ってしまった。まず、前からずっと観たいと思っていてついに初視聴となった鈴木清順の「オペレッタ狸御殿」。いやー、すごかった。ツァイ・ミンリャンに負けず劣らずのすごさだ。その前評判や公開時のアートワークなどから三池崇史の「カタクリ家の幸福」的なしっちゃかめっちゃかなものを想像していたのだが、ドタバタなどでは決してないソリッドな造りのミュージカル、いや、そのタイトルにあるようにオペレッタと呼ぶにこそふさわしいものだった。観ながら「すげー、すげー」を連発していたので、もし聞いている人がいたら相当奇異に思ったことだろう。ぼくはミュージカルは不得意なのだが、ウディ・アレンの「世界中がアイ・ラヴ・ユー」は文句なしに好きだ。「狸御殿」は、きっぱり好きだと言えるミュージカル映画、いやオペレッタとしては(自分にとって)記念すべき2つめの作品となった。それに、もしかしたら、アレンよりも好きかもしれない。ちなみに、イギリス版のDVDには鈴木清順監督の痛々しい呼吸器姿による会見の模様も収録されている。ICAの舞台上で咳き込みながらも、「なぜ狸姫は中国語なんですか?」、「それはチャン・ツィイーさんが中国人だからですよ」しかり、「同じ日活でも今村昌平監督は映画が撮れるようになるまで何年もかかってますが、清順監督は入社後すぐ映画を撮り始めてます。なぜでしょうか?」、「そりゃぼくが今村さんよりも出来がいいからでしょう」などといった清順節も快調である。
敢えてしようと思ってのことでは決してないのだが、今日はいろんなジャンルのゲテモノが揃ってしまった。まず、前からずっと観たいと思っていてついに初視聴となった鈴木清順の「オペレッタ狸御殿」。いやー、すごかった。ツァイ・ミンリャンに負けず劣らずのすごさだ。その前評判や公開時のアートワークなどから三池崇史の「カタクリ家の幸福」的なしっちゃかめっちゃかなものを想像していたのだが、ドタバタなどでは決してないソリッドな造りのミュージカル、いや、そのタイトルにあるようにオペレッタと呼ぶにこそふさわしいものだった。観ながら「すげー、すげー」を連発していたので、もし聞いている人がいたら相当奇異に思ったことだろう。ぼくはミュージカルは不得意なのだが、ウディ・アレンの「世界中がアイ・ラヴ・ユー」は文句なしに好きだ。「狸御殿」は、きっぱり好きだと言えるミュージカル映画、いやオペレッタとしては(自分にとって)記念すべき2つめの作品となった。それに、もしかしたら、アレンよりも好きかもしれない。ちなみに、イギリス版のDVDには鈴木清順監督の痛々しい呼吸器姿による会見の模様も収録されている。ICAの舞台上で咳き込みながらも、「なぜ狸姫は中国語なんですか?」、「それはチャン・ツィイーさんが中国人だからですよ」しかり、「同じ日活でも今村昌平監督は映画が撮れるようになるまで何年もかかってますが、清順監督は入社後すぐ映画を撮り始めてます。なぜでしょうか?」、「そりゃぼくが今村さんよりも出来がいいからでしょう」などといった清順節も快調である。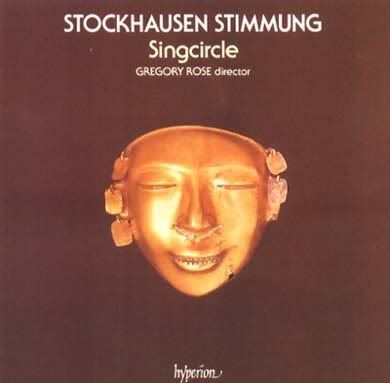 さて本日、もうひとつのキワモノはシュトックハウゼンの「Stimmung」である。ドイツ語ではstimmungというと雰囲気、ムードから<公的な意見>まで、幅広い意味があるそうである。どういう作品かというと、コーラスでヴィシュヌからゾロアスターなど古今東西の神様の名前を連呼するだけという51の断片である。この86年の録音は、6名の声楽家たちが輪になって歌ったものらしいのだが、かなり<唖然とする>作品だ。リゲティ、ノーノ、クセナキスでも、ここまで唖然としないと思う。が、ありがたさも、少しお裾分けしてもらったような気持ちもちょっとする。不思議と飽きずに聞ける74分だった。
さて本日、もうひとつのキワモノはシュトックハウゼンの「Stimmung」である。ドイツ語ではstimmungというと雰囲気、ムードから<公的な意見>まで、幅広い意味があるそうである。どういう作品かというと、コーラスでヴィシュヌからゾロアスターなど古今東西の神様の名前を連呼するだけという51の断片である。この86年の録音は、6名の声楽家たちが輪になって歌ったものらしいのだが、かなり<唖然とする>作品だ。リゲティ、ノーノ、クセナキスでも、ここまで唖然としないと思う。が、ありがたさも、少しお裾分けしてもらったような気持ちもちょっとする。不思議と飽きずに聞ける74分だった。
といった感じで細かいところでは、お昼に食べたのがベイクトビーンズのピザであるとか、今週の「This Diary Will Change Your Life」が「ご近所のゴミを覗いてみよう!」であるとか、30年前の今日はイエロー・マジック・オーケストラの結成日でもあるとか、<重なるときは重なるもんですね>っぽい日。
2008年2月18日月曜日
後世に伝えたい義母のレシピ:トード・イン・ザ・ホール
 これはかなりレトロなイギリス料理で、しかもどちらかというと庶民の食べ物である。逐語訳すれば「穴の中のカエル」という意味だが、体裁としては天ぷらの「ころも」みたいなものの中にソーセージを入れてオーブンで焼いたもの、ということになると思う。ヨークシャープディングというプリンではなく、甘くもないローストビーフの付け合わせのことは、<知ってる人は知ってる>程度のものと思う。「トード・イン・ザ・ホール」は、あれと同じ「ころも」を使うわけである。中産階級出身の友だちに、フィッシュ&チップスやトード・イン・ザ・ホールみたいなものは「貧乏人の食事だよね」と言って憚らないのがいる。まあ、お好み焼きとかと一緒で、安く腹を膨らませるために庶民が考案し、定着してきたという経緯はあるようである。
これはかなりレトロなイギリス料理で、しかもどちらかというと庶民の食べ物である。逐語訳すれば「穴の中のカエル」という意味だが、体裁としては天ぷらの「ころも」みたいなものの中にソーセージを入れてオーブンで焼いたもの、ということになると思う。ヨークシャープディングというプリンではなく、甘くもないローストビーフの付け合わせのことは、<知ってる人は知ってる>程度のものと思う。「トード・イン・ザ・ホール」は、あれと同じ「ころも」を使うわけである。中産階級出身の友だちに、フィッシュ&チップスやトード・イン・ザ・ホールみたいなものは「貧乏人の食事だよね」と言って憚らないのがいる。まあ、お好み焼きとかと一緒で、安く腹を膨らませるために庶民が考案し、定着してきたという経緯はあるようである。
それはともかく、所謂<おふくろの味>的なものでもあるせいだろうと思うが、「トード・イン・ザ・ホール」はレシピ本などにはあまり出ていないものである。ぼくもこの「トード・イン・ザ・ホール」は10年以上前に義母から教わった。どこにも書き留めていないが、簡単なのでまず忘れない。たまに見かけるレシピと比べて義母のレシピの独特なところは、この「ころも」を作るときに水と牛乳を半々にすることである。「そのほうが、牛乳だけよりパリッと仕上がるのよ」。基本の分量は小麦粉4オンス、卵2個、件の水の牛乳割りのようなもの半パイントに塩とふくらし粉をひとつまみずつ。120グラムの粉、280mlの液体くらいに換算できるだろうか。この比率で、「どろっ」と「さらさら」の中間くらいの重さになるはずである。粉のものなので寝かせておくことが肝要だが、これはソーセージを調理している間に寝ていてもらえばいいわけで、順番としてはオーブン余熱→「ころも」を計量、混ぜる→ソーセージ投入→焼けたソーセージに種を流し込む、といった感じ。220度という高温で、ソーセージを大さじ4杯くらいの多めの油で焼く。途中何度かひっくり返すと、ちょうど20分くらいで<きつね色ちょい手前>になっている(はずである)。ここに、寝ててもらった「ころも」を流し込んで急いでオーブンに戻せば30分くらいでトレイからはみ出んばかりに膨らむ(はずである)。
ヨークシャープディングもそうだが、調理には油が必要である。伝統的には牛脂を使うらしいが、ぼくは高温でも焦げにくいガチョウの脂かピーナツ油を使う。スフレなどと同じで、ここでものすごく重要なのはこの「ころも」を入れるトレイが<そりゃあもうあーた>ってくらいにものすごく高温になっていることである。「トード・イン・ザ・ホール」の場合、トレイを熱くするのは決して難しいことではない。前もって、同じトレイでソーセージを焼いておけばいいからだ。手間がかからなくて、すごく簡単。
ちなみに、イギリスには「セルフ・レイジング」というふくらし粉があらかじめ混ぜた状態で売られている小麦粉というのがある。ドイツ人やハンガリー人の友だちにも聞いたのだが、同種のものはドイツやハンガリーにはないそうである。これも初台の友だちと<イギリス料理談義>しているときに出てきたのだが、セルフ・レイジングを使うと薄力粉にベーキングパウダーを混ぜたものとは、若干仕上がりが違う。義母の「トード・イン・ザ・ホール」もセルフ・レイジングなのだが、これに更にふくらし粉を足すわけである。もこもこに膨らんだ「トード・イン・ザ・ホール」にするためなんだろうな、と思う。「トード・イン・ザ・ホール」は、庶民の味とはいえそれなりに歴史のある料理だ。バリエーションも様々で、牛乳と水を混ぜるのもおそらくは義母のオリジナルということでもないとは思う。が、ぼくにとってはこれはあくまでも義母のレシピである。
2008年2月17日日曜日
ご近所探検隊:日曜ブランチは「バナーズ」で
 歩いて15分のクラウチ・エンド。先週までは、2月だというのに昼の気温は13度とかあったのだが、今日は午後まで霜が残っていた。キリリと、潔く晴れている。こうした零下の朝に、ちゃんとした登山靴みたいのを履いて長めの散歩に出かけた後にブランチするとした場合、Bannersに敵うところはまずこの近くではないと思う。ロッケンロールな雰囲気の店内はボブ・ディランのポスターあり、吸っちゃいけないことになったけどラッキーストライクのマシンありで、快活、気さくな感じのものである。
歩いて15分のクラウチ・エンド。先週までは、2月だというのに昼の気温は13度とかあったのだが、今日は午後まで霜が残っていた。キリリと、潔く晴れている。こうした零下の朝に、ちゃんとした登山靴みたいのを履いて長めの散歩に出かけた後にブランチするとした場合、Bannersに敵うところはまずこの近くではないと思う。ロッケンロールな雰囲気の店内はボブ・ディランのポスターあり、吸っちゃいけないことになったけどラッキーストライクのマシンありで、快活、気さくな感じのものである。
ここはまず、いつも混んでいる。平日の午後3時に行こうが週末の朝の10時に行こうが、待たずに座れることはまずない。安いとはとてもいえないと思うが、若い子連れしかり、開店当時からの常連らしき初老のご夫婦と思しき二人連れしかりで、客層もバラエティに富んでいる。基本的には「北米、中米寄り」の朝食メニューが一日中食べられる、というのが売りだ。フライアップというのだが、ベーコン、ソーセージ、卵、ハッシュトポテトだとかが「でん」、と皿から溢れそうな勢いで積まれている朝食。ベジタリアンのためにプランティンという火を通さないと食べられないバナナの一種である野菜バージョンもある。カナダ人の叔父からベーコンにメイプルシロップの話は聞いていたのだが、実際に食べてみたのはここBannersが初めてだった。1999年の冬だったなあ、そういえば。カリブ風のジャークチキンだとか、タイ風のお魚のコロッケのような体裁のものもあって、必ずしもおいしいのはアメリカものばかりではない。それに、テーブルにいろいろ置いてあるソースの類いで最も目を引くの様々なチリソースである。ケチャップやマスタードもあるのだが、ハラペニョソース、マサラ風というインド/マレーシアのもの、ジャマイカの唐辛子たっぷりのサルサなど、唐辛子の入っているソースが振るっているのだ。
ちなみに、今回は時節柄なんだろうか、胸にヒラリー(クリントン)というTシャツを着ているウェイトレスがいた。けっこうおばちゃんなんだけど、なんかかっこよかった。
2008年2月16日土曜日
いつの間にか更新される発音
モレスキンになっていた。英語では相変わらずモールスキンと発音するが、カタカナの表示がどうやらモレスキンに統一される方向に動きつつあるらしい。リナックス、リヌクス、リーヌークス等々はまだ決着してないようではあるものの、世間一般にはリナックスが一番通じるようでもある。日本Linux協会なんて読み方が定着してないからなんだろうなあ、ともちょっと思いつつ、このカナ表記ってのは時々ものすごく曲者だなと思う。
そういえば俳優さんのカナ表記。スティーブ・ブスケミなんてのが横行していた時代もありました。Renée Zellwegerなんて、ゼルウィガーはともかくファーストネームはレニーとかレネーとか表記されるけど、ぼくはルネイだと思う。キーラも、ナイトレーじゃなくてナイトリーだと思うし。ボブ・マーリーは、ぼくが子供の頃はマーレーだったんだよな、そういえば。あと、前にも書いたけどChewetel Ejioforなんて英語圏でもなんて読むのか微妙なナイジェリア系の名前だが、The Internet Movie Databaseにも出ている通りでチュウィテル・エジオフォ、くらいじゃないかと思う。インタビューなどでもチューイと呼ばれてるし。日本でたまに見かけるキウェテルは、ちょっと遠過ぎ。そんな感じで、気分は「広めよう、できるだけ近い発音によるカナ表記大会」である。
それにしてもこのモレスキンのサイト、なにげにweb 2.0っぽくで好きです。
2008年2月15日金曜日
猫とフォーレの意外な関係
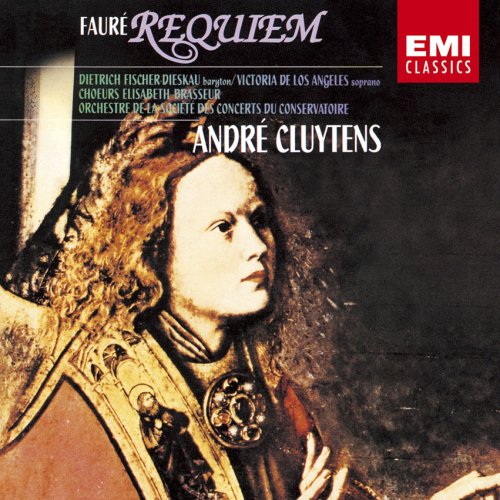 猫が掃除機を怖がるというのは、猫好きでなくとも有名だと思う。今日、アイロンをかけながら何の気なしにかけたフォーレの「レクイエム」で猫が掃除機と同じように怖がって逃げた。ちょっと、意外。たとえば、ヴェルディやモーツァルトのレクイエムでも、猫は逃げない。フォーレの「パヴァーヌ」でも逃げない。レクイエム、しかも「入祭唱とキリエ」で逃げる。最初はハードディスクが人間に聞こえない周波数帯域で雑音でも出しているのかというのも疑ったものの、これはこそらく導入部、ユニゾンのおどろおどろしいコントラバスが怖いんだろうということに落ちついた。
猫が掃除機を怖がるというのは、猫好きでなくとも有名だと思う。今日、アイロンをかけながら何の気なしにかけたフォーレの「レクイエム」で猫が掃除機と同じように怖がって逃げた。ちょっと、意外。たとえば、ヴェルディやモーツァルトのレクイエムでも、猫は逃げない。フォーレの「パヴァーヌ」でも逃げない。レクイエム、しかも「入祭唱とキリエ」で逃げる。最初はハードディスクが人間に聞こえない周波数帯域で雑音でも出しているのかというのも疑ったものの、これはこそらく導入部、ユニゾンのおどろおどろしいコントラバスが怖いんだろうということに落ちついた。
それにしてもk r buxeyのビデオインスタレーションもフォーレのレクイエムだった。なにか「畏怖させる」ものがあるんだろうか。
ちなみに、ぼくが持っているいくつかのフォーレのレクイエムのうち、一番気に入っているのはアンドレ・クリュイタンス指揮のパリ音楽院管弦楽団による1962年録音である。チョン・ミュンフン指揮のサンタ・チェチーリア国立アカデミー管弦楽団(ちっとも控え目じゃないチェチーリア・バルトリ)盤もいいし、ボーイソプラノのコルボ盤も聞いてみたいと思う。ちなみにクリュイタンス盤は有名な録音らしいが、2007年に廉価盤も発売されたようなので、興味があったら永遠の安息をこの「世紀の録音」でぜひ。
2008年2月14日木曜日
今日はバナナブレッド
 個人的に気になるニュースの多い日って、あると思う。2月13日は市川崑が亡くなったこともそうだが、サドラーズ・ウェルズでピナ・バウシュ振付けよる「春の祭典」が始まったり、アレン・ギンズバーグの初録音が見つかったり、エコな携帯電話が発表されたり。そういえば1994年に使い始めた携帯電話だが、初代のモトローラを除いて歴代端末はいつもノキア製だ。なんてったって使いやすい。英紙ガーディアンによると世界の携帯電話は10機中4機がノキア製だそうである。昨日のバルセロナ世界モバイル会議とかってやつで発表になったそうだが、環境に優しいハンドセットのニュース。そういえば生分解性のプラスティックを使った携帯っていうのが何年か前にあったが、あれは実用化されたんだろうか。
個人的に気になるニュースの多い日って、あると思う。2月13日は市川崑が亡くなったこともそうだが、サドラーズ・ウェルズでピナ・バウシュ振付けよる「春の祭典」が始まったり、アレン・ギンズバーグの初録音が見つかったり、エコな携帯電話が発表されたり。そういえば1994年に使い始めた携帯電話だが、初代のモトローラを除いて歴代端末はいつもノキア製だ。なんてったって使いやすい。英紙ガーディアンによると世界の携帯電話は10機中4機がノキア製だそうである。昨日のバルセロナ世界モバイル会議とかってやつで発表になったそうだが、環境に優しいハンドセットのニュース。そういえば生分解性のプラスティックを使った携帯っていうのが何年か前にあったが、あれは実用化されたんだろうか。
でも、そんなことより今日は薫製にした鮭とほうれん草とジャガイモでグラタンを焼いて、バナナブレッドも焼いたこと。グラタンはグリュイエールとナツメグとタラゴンがたっぷり入ったベシャメルである。最近使い始めたばかりなのだが、すんごく気に入っているキプロス産のジャガイモ。薫製の鮭も、所謂スモークサーモンではなく、新鮮な切り身を温薫にしたものだ。<焼き魚に若干煙の匂いがする>的な、火の通った薫製。これをほぐして下茹でしたジャガイモとほうれん草をオーブン皿に順番に散らして、たっぷりめのオリーブ油で軽くカラメル化するまで炒めた紫タマネギとチーズソースで覆う。これにパルミジャーノ・レッジャーノを振りかけて焼く。チーズが焦げやすいので、180度で30分。このレシピは今日の午後、リサーチの仕事をしている間に思いついたものだ。忘れないうちに書き留めて、と。
あと今日、もうひとつ楽しかったのがバナナブレッド。まず信頼できるバナナブレッドのレシピは2つ持っている。どちらも、友だちから伝授されたものである。ひとつはお針子としての才能がズバ抜けているがデザイナーもできるし、Mac使いとしての腕も確かでパリに住んでいたことのある友だちがアメリカ人の友だちから教わったというおそろしく豪快なレシピ。モイスト系ケーキファンのぼくとしてはたまらないレシピである。もうひとつは、ブラジル人の友だちが教えてくれた、計量が適当でも失敗しないおおらかなバナナローフである。今日はこのブラジル版に砕いたペカン(ぼくはピーカンナッツと言ったほうがピンと来る)を混ぜて焼いてみた。粉も、薄力粉とスペルト粉の全粒粉を半々にした。砂糖は、マスコバド糖という精製度の著しく低いもの。沖縄の黒砂糖よりも癖がなくて食べやすい黒砂糖、といった感じだろうか。これにはダークとライトがあって、色もライトの方が明るめだが、このバナナブレッドには通常ライトを使う。まず、250gの粉にふくらし粉とシナモンをそれぞれ小さじ1程度。これが「乾いた具材」。「濡れた具材」のほうはというと、フォークで潰した皮が真っ黒くらいの「アルコール分発生してませんかね?これ」みたいな熟れ過ぎバナナを4本、砂糖は150gで、これに卵を2つ。ここでブラジル風の面白いところは、バターではなくピーナツ油を使うところである。「どぼどぼどぼ、くらい入れるんだよ」と友だちは言う。目けんでは、60mlから90ml前後と言ったところだろうか。乾いた具材に濡れた具材を混ぜてパウンド型に入れ、180度で40分から50分。簡単である。おいしいし。ぜひやってみてくださいまし。
2008年2月13日水曜日
追悼:市川崑監督
 市川崑監督が亡くなった。享年94の大往生だ。ぼくが市川崑を「発見」したのは比較的最近である。子供の頃は横溝正史原作の「犬神家」シリーズだとか、「細雪」などで名前は知っている程度の監督だった。「竹取物語」を沢口靖子で撮ったときには一瞬どうしようかと思ったくらいだ。といった感じで黒澤を「発見」したのがロンドンに来てからだったのと同じで、ぼくが市川崑を発見したのはロンドンに来てからだ。初めて観た市川崑作品は「東京オリンピック」だったのだが、観る前にあからさまな固定観念があった。「オリンピックの記録映画ねえ。クロード・ルルーシュの『白い恋人たち』みたいなもんでしょう?」。今でも覚えている。「東京オリンピック」を見始めて数十分としないうちその固定観念が完膚なきまで破壊された、あの衝撃的なフレームを。台詞らしい台詞はない。スポーツの記録映画であることは確かだが、ドキュメンタリーを超えた何かがある。芸術作品としての評価も高いが、芸術だなんて鯱張ったものでなく、観ていて文句なく面白いのだ。あの語り尽くされている感もある「破壊される東京」といい、2000ミリという超望遠レンズによるクロースアップといい、散りばめられたユーモアといい。3時間近くあるのに、食い入るように観てしまった。
市川崑監督が亡くなった。享年94の大往生だ。ぼくが市川崑を「発見」したのは比較的最近である。子供の頃は横溝正史原作の「犬神家」シリーズだとか、「細雪」などで名前は知っている程度の監督だった。「竹取物語」を沢口靖子で撮ったときには一瞬どうしようかと思ったくらいだ。といった感じで黒澤を「発見」したのがロンドンに来てからだったのと同じで、ぼくが市川崑を発見したのはロンドンに来てからだ。初めて観た市川崑作品は「東京オリンピック」だったのだが、観る前にあからさまな固定観念があった。「オリンピックの記録映画ねえ。クロード・ルルーシュの『白い恋人たち』みたいなもんでしょう?」。今でも覚えている。「東京オリンピック」を見始めて数十分としないうちその固定観念が完膚なきまで破壊された、あの衝撃的なフレームを。台詞らしい台詞はない。スポーツの記録映画であることは確かだが、ドキュメンタリーを超えた何かがある。芸術作品としての評価も高いが、芸術だなんて鯱張ったものでなく、観ていて文句なく面白いのだ。あの語り尽くされている感もある「破壊される東京」といい、2000ミリという超望遠レンズによるクロースアップといい、散りばめられたユーモアといい。3時間近くあるのに、食い入るように観てしまった。
市川崑作品でそれを抜きには語れないというのが、奥方でもあり仕事上でも生涯のパートナーだった脚本家和田夏十だろう。正直、ぼくは和田夏十の脚本のすごさは分らない。プロットは分りやすいけど、言い回しも不自然だし、流れを不必要に滞らせている風なところがあるように思う。でも、不自然だけど、例外的にこれはもう<許す>という感じで観れるのは「黒い十人の女」だ。ぼくは山本富士子の熱狂的なファンである。山本富士子が出ている市川崑作品はほとんど観ていると思う。若干バイアスがかかっているかもしれないが、「黒い十人の女」はピチカートファイヴのファンでなくとも観ておく価値のある傑作だと思う。また、泉鏡花のファンとしては「日本橋」も見逃せない。この映画の発色は、今の映画にはないものだ。当時、技術的にこなれの悪かった大映カラーのおかげで、絢爛豪華だがくすんだ色彩という、今では再現できない美しさを生んでいる。世間に知られているように、この映画はアナクロに溢れているが、アナクロこそがこの映画の魅力でもある。他の市川崑作品では極限状態での飢餓が生むカニバリズムを扱った「野火」、森雅之と新珠三千代主演、夏目漱石の「こころ」もいい。特に「こころ」は、原作を読んだときの読後感とは違った、<市川崑による漱石>という独自の世界だ。現在DVDされていないものとしては東宝で撮った伊藤雄之助主演の「プーサン」(「蒲鉾屋」トニー谷のカメオは、もはやカメオを超えている)、中編「東北の神武たち」なども見逃せない作品だと思う。
個人的には、2つ目の修士論文がイアン・ブレイクウェル著「雪之丞変化」の翻訳だったこともあり、「雪之丞変化」には特に思い入れがある。長谷川一夫の映画出演300本記念作品であり、山本富士子の似合わない「べらんめえ口調」がとてもかわいい。「雪之丞変化」はイギリスにおけるDVD化済み作品としては現在でも唯一の市川崑であるという点においても、特筆に値する。(ちょっとだけに気になっているのだが、タッキーの2008年のNHKお正月時代劇はどうだったんでしょうね。)ちなみに、ぼくが観た市川崑最近作は黒澤明脚本の「どら平太」だ。黒澤明、小林正樹、木下恵介、市川崑という当時の日本映画を代表する4人の巨匠が結成した「四騎の会」。その第1回作品として企画されていた山本周五郎の原作による痛快長編時代劇が「どら平太」だった。結局これは実らず、「四騎の会」の第一作は黒澤の初カラー作品、同じ山本周五郎原作の「どですかでん」になり、興行的に大失敗に終わった。不幸にも、4人はその後「四騎の会」として活動することはなかった。2001年のアダム・ロウ監督の「Kurosawa」というドキュメンタリーの中でも市川崑は「あれ(「どですかでん」)はいい作品だけど、ちょっと暗い。ぼくは四騎の会の一作目は明るく派手に行きたかった」という内容の発言もしている。「どら平太」には雪辱戦的な、映画の出来そのものだけで済まされない因縁めいたものがあるのだ。
ところで、市川崑は岸恵子主演の「かあちゃん」が長編では遺作ということになると思う。まだ観てないので、機会があったらぜひ観てみようと思う。合掌。
2008年2月12日火曜日
マルメロのシロップ煮
 マルメロは英語ではクインス(quince)という、南国系だがイギリスでもポピュラーな冬の果物である。カタチは洋梨のようでもあるが、生では食べられない。加熱して食べる。スペインではマルメロを煮て自然に固まったものを、ドン・キホーテも愛したというマンチェゴチーズと一緒に食べる。この、英語で言うクインスチーズは甘酸っぱくて、羊のミルクのマンチェゴチーズにとても良く合う。ギリシャでは、煮込んだものをジュレのようにして、ヨーグルトと一緒に食べる。ぼくが気に入ってるのはイギリス伝統のお菓子であるライスプディングという甘いお粥のような体裁のデザートと一緒に食べるという方法である。マルメロは比較的大きめの果物なので、2人分作るのにマルメロひとつくらいで十分である。
マルメロは英語ではクインス(quince)という、南国系だがイギリスでもポピュラーな冬の果物である。カタチは洋梨のようでもあるが、生では食べられない。加熱して食べる。スペインではマルメロを煮て自然に固まったものを、ドン・キホーテも愛したというマンチェゴチーズと一緒に食べる。この、英語で言うクインスチーズは甘酸っぱくて、羊のミルクのマンチェゴチーズにとても良く合う。ギリシャでは、煮込んだものをジュレのようにして、ヨーグルトと一緒に食べる。ぼくが気に入ってるのはイギリス伝統のお菓子であるライスプディングという甘いお粥のような体裁のデザートと一緒に食べるという方法である。マルメロは比較的大きめの果物なので、2人分作るのにマルメロひとつくらいで十分である。
さて、このマルメロだが、まずカボチャのように硬い。皮を剥いて芯を外すのだが、かなり剥きにくいし、外しにくい。手を切らないように注意して、日本で食べるリンゴのような形に切ってレモンを搾り、非精製糖の砂糖水で煮ると数十分で柔らかくなる。これをナツメグがたっぷり入ったライスプディングの上に乗せて食べる。 ところでこのライスプディングは調理に時間がかかる。オーブンに入れておくだけなので手間はかからないが、時間はまず1時間以上はかかるので、思いつきで煮てみたマルメロには追いつかない。今回は、まず八角を入れてマルメロを煮て、ギリシャで食べる方法を応用して、ギリシャヨーグルトにピスタチオ、削ったミルクチョコを散らしてみた。旨かった。
ところでこのライスプディングは調理に時間がかかる。オーブンに入れておくだけなので手間はかからないが、時間はまず1時間以上はかかるので、思いつきで煮てみたマルメロには追いつかない。今回は、まず八角を入れてマルメロを煮て、ギリシャで食べる方法を応用して、ギリシャヨーグルトにピスタチオ、削ったミルクチョコを散らしてみた。旨かった。
2008年2月11日月曜日
ご近所探検隊:Chairman Mau Mau
 すばらしい。なにがどうトチ狂うと、こんな店がクラウチエンドとフィンズベリー・パーク間の住宅地なんかに存在できるのだろうか。はっきりいつオープンしたのかは不明だが、店らしいものが姿を見せ始めたのは2007年の暮れ頃だ。「らしい」というのは、それが一見店には見えないからである。それに、開いているのかどうかも判然としなければ、実際週の半分以上はシャッターが閉まっている。屋号はChairman Mau Mau。この屋号、その面白さはかなり翻訳しにくいと思う。ダブルミーニングだし、歴史的なコンテクストにその面白さが大きく依存しているからだ。まず何のお店なのかというと、椅子を売っているお店である。椅子を売っているお店なのでチェアマンというのはもちろんだが、英語でいう毛沢東主席(Chairman Mao)、その主席の「席」と椅子をかけているわけである。そして、Mau Mauというのは1952年から1960年まで続いた反英ケニア暴動のことである。これはまさにミッドセンチュリー、ちょうどイームスの椅子がデザインさ れ、世に送り出された時期に呼応する。それにしてもこのお店、売っているのは椅子だけで、それもヴィンテージのイームスばかりである。グラスファイバー製のようだし、現在は生産されていない色のようだし、なによりその<よれ具合>から察するに、おそらくはすべてオリジナルか70年代までに生産されたものであろうと思われる。店内にはDSR、DARを始め、ワイヤーのDKRやDKXもある。LCM/DCMからEA106やEA108などがあることもある。
すばらしい。なにがどうトチ狂うと、こんな店がクラウチエンドとフィンズベリー・パーク間の住宅地なんかに存在できるのだろうか。はっきりいつオープンしたのかは不明だが、店らしいものが姿を見せ始めたのは2007年の暮れ頃だ。「らしい」というのは、それが一見店には見えないからである。それに、開いているのかどうかも判然としなければ、実際週の半分以上はシャッターが閉まっている。屋号はChairman Mau Mau。この屋号、その面白さはかなり翻訳しにくいと思う。ダブルミーニングだし、歴史的なコンテクストにその面白さが大きく依存しているからだ。まず何のお店なのかというと、椅子を売っているお店である。椅子を売っているお店なのでチェアマンというのはもちろんだが、英語でいう毛沢東主席(Chairman Mao)、その主席の「席」と椅子をかけているわけである。そして、Mau Mauというのは1952年から1960年まで続いた反英ケニア暴動のことである。これはまさにミッドセンチュリー、ちょうどイームスの椅子がデザインさ れ、世に送り出された時期に呼応する。それにしてもこのお店、売っているのは椅子だけで、それもヴィンテージのイームスばかりである。グラスファイバー製のようだし、現在は生産されていない色のようだし、なによりその<よれ具合>から察するに、おそらくはすべてオリジナルか70年代までに生産されたものであろうと思われる。店内にはDSR、DARを始め、ワイヤーのDKRやDKXもある。LCM/DCMからEA106やEA108などがあることもある。
というわけでおよそ店らしくないのだが、開いてるといつ見ても楽しい。不定期でしか開いてない上、開いていても紙切れに「ばんばんドアを叩くか、この携帯にかけて」と番号が書いてあるだけだ。商売っ気のカケラもない。しかも、住宅地の外れ、路線ひとつだけのバス通りのちょうど曲がり角というものすごく鬼門っぽいところに位置しており、お店の中にはオールドスクールな大型のスピーカーとターンテーブル、数十枚のレコードに0号か1号程度の大きさのカンバスの抽象画が何点か置いてあるだけである。ぼくがお店の前を通りかかったときに、中に人がいたことはない。今度お店の人がいたらいろいろ詳しく聞いてみようと思う。
2008年2月10日日曜日
見落とされがちな要素
 さて、ここで問題です。映画「シド・アンド・ナンシー」、「ショーシャンクの空に」、「ジェシー・ジェームズの暗殺」をつなげるものとは、いったい何でしょうか?この段落を読み終わる前に答えてください。ちくたく、ちくたく。って、これはかなりの映画好きでないと答えられない質問なのではないかというのを期待しているわけだが、なんだと思います?今これを書いているただ中、テレビでBAFTAの授賞式が放映されている。そのとき、思わず拍手してしまったことがあるのだ。贈られた人へ「大変良くできました」的なこともあるのだが、この賞をその人に与えたというBAFTAの審査員にこそ贈りたい拍手である。それにしても「映画に限って言えば」だが、今年はかなり珠玉の名作揃いの当たり年なんじゃないだろうか。今年のBAFTAの「つぐない」が最優秀映画賞は、、、まあ、、、それはね、、、とは思いつつも、「やっぱりね」のその<やっぱり>に必然性がすごく感じられる受賞が多い気がする。ダニエル・デイ=ルイスの最優秀主演男優賞しかり、ハビエル・バルデムの最優秀助演男優賞しかり。
さて、ここで問題です。映画「シド・アンド・ナンシー」、「ショーシャンクの空に」、「ジェシー・ジェームズの暗殺」をつなげるものとは、いったい何でしょうか?この段落を読み終わる前に答えてください。ちくたく、ちくたく。って、これはかなりの映画好きでないと答えられない質問なのではないかというのを期待しているわけだが、なんだと思います?今これを書いているただ中、テレビでBAFTAの授賞式が放映されている。そのとき、思わず拍手してしまったことがあるのだ。贈られた人へ「大変良くできました」的なこともあるのだが、この賞をその人に与えたというBAFTAの審査員にこそ贈りたい拍手である。それにしても「映画に限って言えば」だが、今年はかなり珠玉の名作揃いの当たり年なんじゃないだろうか。今年のBAFTAの「つぐない」が最優秀映画賞は、、、まあ、、、それはね、、、とは思いつつも、「やっぱりね」のその<やっぱり>に必然性がすごく感じられる受賞が多い気がする。ダニエル・デイ=ルイスの最優秀主演男優賞しかり、ハビエル・バルデムの最優秀助演男優賞しかり。
ってまあそれはいいとして、そろそろ答えの時間にしましょうか。上記三作品に共通するのは「撮影監督が同じ人」、でした。この三作品を撮った撮影監督が、コーエン兄弟の最新作「ノー・カントリー」で最優秀撮影賞を受賞したのだ。すごく地味で、ちょっとアンチクライマックスっぽい答えで恐縮だが、これはそれなりの意味を持つ持つ受賞だったと、個人的には思う。その人の名はロジャー・ディーキンス。「バートン・フィンク」以来、コーエン兄弟作品の撮影はすべてこの人がやっている。
それにしても、映画にとって撮影というのは、視覚的な部分ではそれがすべてと言っていいほど映画の根幹をなすものでありながら、見る者にとってそれが意識されないものというパラドックスを感じる。よほどの映画好きか、丸っきりの映画業界人(その筋の人、とも言う)でもない限り、映画を観終わって「いい映画だったなあ」とは思っても、「この映画<撮影>が良かったよなあ」とは思わないものなんじゃないだろうか。逆に、「いい映画だったよなあ」と、撮影を意識しないで撮れる撮影監督こそ凄いのかもしれない。たとえば、黒澤明は東宝争議のとき大映において、かのベネチアでグランプリを受賞した「羅生門」を宮川一夫で撮っている。こういうのは、オタク的に知っていればこそ意味があるが、撮影監督の存在はあくまでも裏方であってこそ、なんじゃないだろうか。そこへ、今回のロジャー・ディーキンスの撮影賞受賞はすごく「観ている人は観ている」を感じさせるものだったように思う。今回のBAFTAや主要な映画賞からは徹底的に無視されている「ジェシー・ジェームズの暗殺」も、受賞作であるコーエン兄弟の新作「ノー・カントリー」も、ロジャー・ディーキンスなのだ。この、観てすぐそれと分るほどの灰汁の強さはないものの、真っ当な仕事を地に足をつけてこなしている職人の仕事が認められたというのは、一ファンとしてとてもうれしい。
それにしてもBAFTA授賞式でティルダ・スウィントンが着ていたディオールはものすごくゴージャスだった。あれに負けないパーソナリティだというのがまたすごい。でもタンディ・ニュートンのアレクサンダー・マクィーンが個人的にはすごくかわいかった。あと、今年はやけにジャスミン・ディ・ミロが多かった気がする。ちょっと注目しちゃおうかしら。
2008年2月9日土曜日
ピンターの舞台、二本立て
 ハロルド・ピンターの舞台を観にいくのは昨年の夏の「背信(Betrayal)」以来だ。ピンターは、ものすごく賢いダイアログに、切れ、冴えとも最高峰だろうと思しきストーリーテリングの妙に尽きると思う。不条理劇という読みもあるようだが、敢えて分りにくい状況設定で、観終わったあと「実際のところはどうなんだろう?」と考えたり、話し合ったりすることこそが魅力だと思う。
ハロルド・ピンターの舞台を観にいくのは昨年の夏の「背信(Betrayal)」以来だ。ピンターは、ものすごく賢いダイアログに、切れ、冴えとも最高峰だろうと思しきストーリーテリングの妙に尽きると思う。不条理劇という読みもあるようだが、敢えて分りにくい状況設定で、観終わったあと「実際のところはどうなんだろう?」と考えたり、話し合ったりすることこそが魅力だと思う。
さて、今回のお題目は中編の戯曲「The Lover」(1963年)と「The Collection」(1961年)を二本立てにしたというものである。1月の中旬から始まったのだが、やっとマチネーが取れたので行ってきた。ヘイマーケットをちょっと外れたパントン・ストリートに1881年から建っているコメディ・シアターでの上演である。主演はジーナ・マキー(最近の作品では映画「つぐない」にも出ている。「ノッティング・ヒルの恋人」では車いすに乗っていた)にリチャード・コイル。それにチャーリー・コックスという若手と重鎮ティモシー・ウェストの4名によるピンターとくれば、もう「行くしかねえ」である。
感想はというと、一言で言って凄くおもしかった。ちょっとシュールな話(tale)の展開もそうだが、話の伝え方(teller、すなわち演技や演出などのライブの要素)がいい。芝居も申し分ない。「The Lover」は基本的に2人しか出てこないが、中心人物は妻であるサーラだ。ジーナ・マキーを舞台で観たのは始めてだったが、舞台女優としても映画やテレビ作品で見せる<妙に落ち着かない気持ちにさせる>演技こそが、この人の魅力だと思う。「The Lover」で夫を演じるリチャード・コイルは、次の「The Collection」で全く違ったタイプの人物を演じるのだが、この変わり身がまた凄い。ちょっと同じ人とは思えないくらい違う。
ドタバタでは決してないが、ちょっとオトナの笑いがふんだんに散りばめられている。音楽の使い方も良かった。密室劇的な展開だが、舞台ならではの臨場感。いや、実に楽しかった。ロンドンに住んでいて、ラッキーだなと思うことの一つ。
2008年2月8日金曜日
「トンボ」という名の
 ジュースバーなのだが、ハイゲートヴィレッジに最近できたオーガニックの八百屋さんの奥が茶店になっている。というか、知らないと奥にカフェがあるようにはまず見えない。なにしろ、去年まではぼくもそうと知らずに入ってすぐのお店で買い物だけしていた。たとえば、いつも使っている生分解性の食器洗いの洗剤はどこでも売っているものではない(メーカーが家族経営の独立系で、生産規模が小さいせいもあるようなのだが)。このオーガニック屋さんで売っていることに気づいて以来、ここで買っている。近所で買うよりも安いし、スーパーを儲けさせるよりはこういう個人経営っぽいお店にこそ投資したいし。で、このお店はDragonflyというのだが、お茶のメーカーと同じ名前である。しかし、全くの無関係らしい。ま、トンボっていう鉛筆屋さんもあるくらいだし、そこら辺は偶然ってもんでしょう。で、八百屋さん部分だが、化粧品みたいのもある。小さい店舗に、ゆったりめだが無駄のない範囲でいろいろ詰め込んである感じ。もちろん旬の野菜や果物も置いてあるが、目を引くのは入ってすぐ右側の様々な種類のパンだ。そのほとんどは、石臼挽きの粉と天然酵母のパンである。ずっしり重ためのサワードウ、ライ麦パン等々。店員さんもフレンドリーで、場所柄きちんとした身なりだが、気取りがない。
ジュースバーなのだが、ハイゲートヴィレッジに最近できたオーガニックの八百屋さんの奥が茶店になっている。というか、知らないと奥にカフェがあるようにはまず見えない。なにしろ、去年まではぼくもそうと知らずに入ってすぐのお店で買い物だけしていた。たとえば、いつも使っている生分解性の食器洗いの洗剤はどこでも売っているものではない(メーカーが家族経営の独立系で、生産規模が小さいせいもあるようなのだが)。このオーガニック屋さんで売っていることに気づいて以来、ここで買っている。近所で買うよりも安いし、スーパーを儲けさせるよりはこういう個人経営っぽいお店にこそ投資したいし。で、このお店はDragonflyというのだが、お茶のメーカーと同じ名前である。しかし、全くの無関係らしい。ま、トンボっていう鉛筆屋さんもあるくらいだし、そこら辺は偶然ってもんでしょう。で、八百屋さん部分だが、化粧品みたいのもある。小さい店舗に、ゆったりめだが無駄のない範囲でいろいろ詰め込んである感じ。もちろん旬の野菜や果物も置いてあるが、目を引くのは入ってすぐ右側の様々な種類のパンだ。そのほとんどは、石臼挽きの粉と天然酵母のパンである。ずっしり重ためのサワードウ、ライ麦パン等々。店員さんもフレンドリーで、場所柄きちんとした身なりだが、気取りがない。
というわけで始めて入ってみた、奥の茶店の部分。せっかくジュースバーなのでスムージーっぽいものを頼んだのだが、そこら辺のスムージーほどこってりしていなくて飲みやすい。全粒粉のラズベリーマフィンも砂糖を使ってないんだそうで、サクッといただけてしまった。ハイゲートハイストリートの24番。うちから歩くと、片道40分かかる。ちょうどいい散歩コース。
2008年2月7日木曜日
ラジャスタンからやってきた
 操り人形。インド料理屋さんの天井からぶら下がっている。数百体はあるそうである。「マサラゾーン」はソーホーを始め、ロンドン市内に数店舗ある。まあチェーン店といえばそうだが、2007年9月にオープンしたフローラルストリートにあるコヴェント・ガーデン店は、内装に最もインパクトのある店だろう。ロイヤルオペラハウスの横にこんなものがあったら、それは目を引くと思う。ランチと午後6時半までの2コースは8ポンド35ペンス。悪くない。カレーは、当たり外れがないもののような印象もあるが、実際はかなり当たり外れがあると思う。基本的に、レビューはなんでも信用できるTimeOutの情報によると、それなりにポイントも高いようでもある。今度行ったときに確かめてみよう。
操り人形。インド料理屋さんの天井からぶら下がっている。数百体はあるそうである。「マサラゾーン」はソーホーを始め、ロンドン市内に数店舗ある。まあチェーン店といえばそうだが、2007年9月にオープンしたフローラルストリートにあるコヴェント・ガーデン店は、内装に最もインパクトのある店だろう。ロイヤルオペラハウスの横にこんなものがあったら、それは目を引くと思う。ランチと午後6時半までの2コースは8ポンド35ペンス。悪くない。カレーは、当たり外れがないもののような印象もあるが、実際はかなり当たり外れがあると思う。基本的に、レビューはなんでも信用できるTimeOutの情報によると、それなりにポイントも高いようでもある。今度行ったときに確かめてみよう。
2008年2月6日水曜日
まだ観てない「めぐり逢う朝」
 Sainte Colombeのカナ表記自体に問題があるのかもしれないが、ムシュー・ド・サント=コロムという作曲家でありヴィオラ・ダ・ガンバ奏者だったフランス紳士のことは、あまり知られていないようである。「ちょっと調べてみました」程度の範囲ではあるが、本国フランスでもあまり知られていないようだし、英語の情報も限られている。日本語の情報源に至っては、ジェラール・ドパルデューら出演の映画以外のことはついに発見できなかった。日本版のDVDも絶版のようで、アマゾンでも大プレミアが付いている。で、この映画の主人公はマラン・マレで、サント=コロムさんはマレさんの師であったということだが、ぼくはこのマラン・マレが誰かも知らない。ガンバにしても、フランス語なのでヴィオールになっているが、大体ムシューと来られては、知らない人にはそれが作曲家の名前にすら見えないと思う。その後の調べでどうやらファーストネームは「ジャン」らしいことが分ったが、音楽史家の間でも<これが決定版>という情報はないらしい。どうやら、<謎に包まれた>作曲家のようだ。
Sainte Colombeのカナ表記自体に問題があるのかもしれないが、ムシュー・ド・サント=コロムという作曲家でありヴィオラ・ダ・ガンバ奏者だったフランス紳士のことは、あまり知られていないようである。「ちょっと調べてみました」程度の範囲ではあるが、本国フランスでもあまり知られていないようだし、英語の情報も限られている。日本語の情報源に至っては、ジェラール・ドパルデューら出演の映画以外のことはついに発見できなかった。日本版のDVDも絶版のようで、アマゾンでも大プレミアが付いている。で、この映画の主人公はマラン・マレで、サント=コロムさんはマレさんの師であったということだが、ぼくはこのマラン・マレが誰かも知らない。ガンバにしても、フランス語なのでヴィオールになっているが、大体ムシューと来られては、知らない人にはそれが作曲家の名前にすら見えないと思う。その後の調べでどうやらファーストネームは「ジャン」らしいことが分ったが、音楽史家の間でも<これが決定版>という情報はないらしい。どうやら、<謎に包まれた>作曲家のようだ。
というわけで先日、ちょっとした因縁でムシュー・ド・サント=コロムのヴィオールのCDを入手した。しかしこれ、ちょっと面白い内容である。タイトルは「Pièces de viole」。2005年に、ベルギーで録音されたものである。パオロ・パンドルフォというガンバ奏者とテオルボのトマス・ボイセンによる演奏。17世紀後半の音楽ということで、バロックではあるが、ちょっと耳慣れない音楽だ。というのも、なんとなく<新しい>からである。こういう音楽は現代に作曲されたものにも似たようなものがある。下手したらどこぞのBGMにも聞こえるが、決して安っぽいものではない。ギターとガンバという組み合わせも、なんとなく知っているような気がするのに、まったく聞いたことのない類いの音楽として体現されている。といった感じで俄然興味がわいた。まずは「めぐり逢う朝」から始めて見ようと思う。しかしこれ手に入るかなあ。
2008年2月5日火曜日
今日はパンケーキの日
 出ちゃいましたね、iPhoneの16GBとiPod touchの32GB。これは時間の問題だったのかなあと横目で見つつ、16GBになってもGPRSじゃねえ、と、すぐさま移るは今日のお題のパンケーキ。まず思ったのが、「英語のpancakeとカタカナのパンケーキって、果たして同じ意味だろうか?」、という疑問である。英語のpancakeというのはホットケーキみたいのとは違って、見た目といい、味といい、まんまクレープだが、日本人の持つパンケーキの印象はどうだろう?大体、カタカナでパンケーキという言葉が存在してるんだろうか?
出ちゃいましたね、iPhoneの16GBとiPod touchの32GB。これは時間の問題だったのかなあと横目で見つつ、16GBになってもGPRSじゃねえ、と、すぐさま移るは今日のお題のパンケーキ。まず思ったのが、「英語のpancakeとカタカナのパンケーキって、果たして同じ意味だろうか?」、という疑問である。英語のpancakeというのはホットケーキみたいのとは違って、見た目といい、味といい、まんまクレープだが、日本人の持つパンケーキの印象はどうだろう?大体、カタカナでパンケーキという言葉が存在してるんだろうか?
ところでこのパンケーキの日だが、まず「マルディ・グラ」という言葉は、イギリス英語では使わない。逆に、アメリカで「パンケーキの日」と言っても通じない。同じもののことだけど。これは四旬節、英語ではレントという英国国教会系プロテスタントにおける復活祭にまつわる習慣なのだが、この移動祝日ってやつがものすごく複雑怪奇である。教会に深い関わりのある義父もその年の四旬節がいつから始まるのかという計算方法は知らないそうである。つまり、市井の人には「今年はこの日からですよ」と言われない限りは分らないものらしい。
そもそもパンケーキの日というのは俗称で、Shrove Tuesdayというのが正式名称である。復活祭の46日前に始まる四旬節の最初の日「灰の水曜日」の前日の火曜日に、パンケーキを食べるという習慣で、旧宗主国のカナダ、オーストラリアなどでも続いている習慣のようである。なぜパンケーキなのかというと、四旬節の期間は断食するというのが古来の習慣だったが、それが「一番の好物をその期間は食べない」に変わったのだと言う。その前に、リッチな食材だった卵や粉を片付けてしまう、というのが由来らしい。ちなみに義父はマーマーレードが好きなので、明日から46日間はマーマーレードを食べないことになる。友だちも「しばらく食べられなくなるし、無駄にしたくないから」と、ぼくの作ったチョコトリュフの残りを一気食いしたそうである。
ところでこのクレープ状のパンケーキ、基本はシンプルにレモン汁と砂糖で食べる。でも先日いただいたたくさんベリーのジャムもあるのでそれも付けて食べる。ぼくは四旬節関係ないんだけどね。
2008年2月4日月曜日
自分的中国茶の世界
 そういうわけでお茶は基本的になんでも好きなのだが、中国茶のことはハサミ研ぎの元締めから教わった。新潟の燕市で採取される砂鉄を原料に作る美容師さんのハサミ。日本国内で全部仕上げるのと、工程により仕上げは台湾で行うものとある。コストの問題ももちろんだが、場合によっては台湾製の方が精度が高かったりするのだ。研ぐ方としても、正直研ぎやすいのは台湾製である。原料は同じなのだが微妙な違いがどこかで生まれてくる。で、この大阪人の元締めは仕事でなくても台湾には好きで行くくらいの人で、北西ロンドン巨大サッカー場のあるウェンブリーの大邸宅にお住まいである。この人のご自宅で台湾の青茶をいただいたのも、そろそろ10年くらい前になると思う。今まで、全く知らない味だった。水色だって青茶とは良く言ったもので、緑茶の黄緑とは全く違う青みである。程よい甘みがあり、おままごとのように小さいお猪口のような茶碗でいただくのだが、一煎ごとに味が変わる。でも、それは「ウーロン茶」なのだという。ぼくの知ってるウーロン茶はあのサントリーの茶色くてヤケに渋くて、というものだったのでものすごくびっくりした。それは凍頂烏龍という、それこそ富士山より高いかもしれないくらいの高山で取れる、「高山茶」というものだったのだ。
そういうわけでお茶は基本的になんでも好きなのだが、中国茶のことはハサミ研ぎの元締めから教わった。新潟の燕市で採取される砂鉄を原料に作る美容師さんのハサミ。日本国内で全部仕上げるのと、工程により仕上げは台湾で行うものとある。コストの問題ももちろんだが、場合によっては台湾製の方が精度が高かったりするのだ。研ぐ方としても、正直研ぎやすいのは台湾製である。原料は同じなのだが微妙な違いがどこかで生まれてくる。で、この大阪人の元締めは仕事でなくても台湾には好きで行くくらいの人で、北西ロンドン巨大サッカー場のあるウェンブリーの大邸宅にお住まいである。この人のご自宅で台湾の青茶をいただいたのも、そろそろ10年くらい前になると思う。今まで、全く知らない味だった。水色だって青茶とは良く言ったもので、緑茶の黄緑とは全く違う青みである。程よい甘みがあり、おままごとのように小さいお猪口のような茶碗でいただくのだが、一煎ごとに味が変わる。でも、それは「ウーロン茶」なのだという。ぼくの知ってるウーロン茶はあのサントリーの茶色くてヤケに渋くて、というものだったのでものすごくびっくりした。それは凍頂烏龍という、それこそ富士山より高いかもしれないくらいの高山で取れる、「高山茶」というものだったのだ。
ぼくが始めて台湾に行ったのは2005年の初頭のことだ。日本に住んでる間は良く行っていた茶藝館「華泰茶荘」の本店にも行った(台北店は茶藝館ではなく、茶器とお茶を売っているだけ)。はっきり言ってヘネシーとかレミーマルタンよりも高い15年もののプーアル茶だとか青磁の茶杯なんかを仕入れた。茶壺は、「ちゃふう」と読む。所謂急須のことだが、宜興紫砂の鳩口水平、朱の円珠、黄の匏(うり)急須なんかは華泰茶荘の渋谷店で仕入れた。ちなみにこのお店は、道玄坂を登りきった左手の、ほとんど神泉という場所にある。リリアン糸みたいなもので蓋も編んでもらった。誠にもって、職人の技である。お茶の種類によっては「蓋碗(がいわん)」という蓋付きのお茶碗のような体裁のものを急須として、蓋をずらして注ぐのだが、ぼくは使ってない。なんだか上手く注げないし、急須が好きだし。その他の茶器では聞香杯(匂いを嗅ぐための細長い茶碗)と茶盤(急須にお湯を欠けて蒸らすので、水受けにする)、茶海(小さい茶杯に均等に注ぐためのピッチャー)はプランタン銀座の中にあったチンシャンというところで仕入れた。茶葉は華泰茶荘のほかではルピシア。かの表参道ヒルズの真向かいにある「遊茶」というお店も、ちょっとオシャレでおススメ。
ティースミスのことは前にも紹介したが、ロンドンでもやっとのことで探しだした中国茶のお店はメイフェアと、このティースミスだ。武夷水仙、東方美人、名間金萱などは大体どちらかで仕入れている。さて、今日は青磁の茶壷でいれた鳳凰単叢。ワインみたいに採れた年で全然味の違うお茶である。これは2004年もの。晴れてるし、猫も眠そうだし、グラスでぐびぐび飲んだ。日本から運んできたものなのだが、残念ながらこれで最後である。 お茶うけはナツメヤシ、干しイチジク、カボチャの種、練り山査子、蓮の実の甘納豆なんかが気に入っている。でも、後者2つはまずロンドンではお目にかかれない。特に蓮の実の甘納豆。これは日本にいたときでさえ、中々入手は困難だった。未知のお茶うけを探す旅。中華街なんかに、また探りを入れてみようと思う。そういえばあのパンダンの葉っぱの入ったシフォンみたいなやつ、合うかもしれない。
お茶うけはナツメヤシ、干しイチジク、カボチャの種、練り山査子、蓮の実の甘納豆なんかが気に入っている。でも、後者2つはまずロンドンではお目にかかれない。特に蓮の実の甘納豆。これは日本にいたときでさえ、中々入手は困難だった。未知のお茶うけを探す旅。中華街なんかに、また探りを入れてみようと思う。そういえばあのパンダンの葉っぱの入ったシフォンみたいなやつ、合うかもしれない。
2008年2月3日日曜日
「考える」を「オシャレに」すると
 定期的に、というほどではないのだが、購読している雑誌に「Monocle」がある。モノクル、片眼鏡なんていうと、ぼくなんかすぐ東京創元社、ポプラ社刊「奇巌城」、モーリス・ルブラン作アルセーヌ・ルパンなんかが頭にずらずら浮かんでしまうのだが、雑誌は怪盗とは全く無関係である。ところでこの「Monocle」は、ちょっとカテゴリーにはめにくい雑誌である。「片眼鏡」という雑誌名が象徴的に示すように、フィルターされた視点で国際情勢、デザイン、「人生の価値インデックス」みたいなことを取り上げてはいる。見た目も一見ビジネス雑誌で、本屋さんや駅のマガジンスタンドに行っても「The Spectator」みたいなカタい雑誌の横に並んでたりもする。ところがこれはフェイントで、毎号出ているので連載と言っていいであろう劇画タッチの漫画もあれば、東京シティエアターミナル行きのリムジンバスが特集されていたり、アフガニスタンの構造的に問題のあるナルシスティックな<お城風の一軒家>が出ていたり、軽く訳が分らない。ちなみにこのリムジンバス、車内アナウンスがMonocleのサイトから直接聞けるようにもなっている。どこまで本気なのか迷うところだが、どうやら編集部の人たちは大マジである。
定期的に、というほどではないのだが、購読している雑誌に「Monocle」がある。モノクル、片眼鏡なんていうと、ぼくなんかすぐ東京創元社、ポプラ社刊「奇巌城」、モーリス・ルブラン作アルセーヌ・ルパンなんかが頭にずらずら浮かんでしまうのだが、雑誌は怪盗とは全く無関係である。ところでこの「Monocle」は、ちょっとカテゴリーにはめにくい雑誌である。「片眼鏡」という雑誌名が象徴的に示すように、フィルターされた視点で国際情勢、デザイン、「人生の価値インデックス」みたいなことを取り上げてはいる。見た目も一見ビジネス雑誌で、本屋さんや駅のマガジンスタンドに行っても「The Spectator」みたいなカタい雑誌の横に並んでたりもする。ところがこれはフェイントで、毎号出ているので連載と言っていいであろう劇画タッチの漫画もあれば、東京シティエアターミナル行きのリムジンバスが特集されていたり、アフガニスタンの構造的に問題のあるナルシスティックな<お城風の一軒家>が出ていたり、軽く訳が分らない。ちなみにこのリムジンバス、車内アナウンスがMonocleのサイトから直接聞けるようにもなっている。どこまで本気なのか迷うところだが、どうやら編集部の人たちは大マジである。
最新号は第10号だが、表紙はご覧の通り新幹線だ。東京にも編集部があるらしいが、第8号にはタイクーングラフィックスの宮師雄一氏のインタビューが出ていたり、ポストモダンなスーパーのカタチとして東急のPrecceが紹介されていたりもする。エディトリアルだけではない。ものすごく上質の紙と精細な印刷技術で、手抜きは一切なし。洋書扱い店だとかで見かけたら、ぜひ手に取ってみてくださいまし。
2008年2月2日土曜日
「百度」という検索エンジン
ヤフーの買収防止作戦なんかも世間を賑わしているようではあるが、それはよそに中国の検索サイトの日本語サービスが始まったようである。baidu.jpというらしいが、「社名の由来」ページによると、
「百度(Baidu)」の名前は、この中国宋時代の古い漢詩の一節に由来しています。だそうである。なるほど、ポエティック。GoogleとかYahoo!とかの他に、ぼくが使うのAskとかだが、機能的には遜色ないようだし、GUIもGoogle的で見慣れているせいか、すっきり見やすい。試しに検索したのは時節柄「スーパーチューズデー」という語句。速い。カタカナだとちゃんとウィキペディアのエントリがトップである。Super Tuesdayを英語でも検索してみたが、トップにひっかかってきたのは大統領選ではなく、バンドだった。傾向というものが伺える。速さだとかだけじゃない、差別化はまだ発見できてないが、ちょっと続けて使ってみると面白そうな検索サイトかもしれない。
「…人込みの中を幾度となく探し回った。ふと振り返ると、あの人はいた 消え入りそうな灯火のそばに」
2008年2月1日金曜日
野ウサギのラグー
 カタカナでの使用と、英語での意味がかなり違うシリーズ。まず、ラグーとは言っても、あの瓶に入ってるパスタソースのブランドのことではなく、肉をベースにしたソース全般を指す極一般的なイタリア語なわけで、英語でもそのまま使われるが「パスタソースでしょ?」という人は英語圏にもいるのでまあ、その辺は。それと、今回のテーマで問題なのはgameという英単語である。これは、かなり日本語にならない。一般的にはもちろんスポーツのゲーム、遊戯、競技のようなことを意味するが、gameには「狩猟の対象となる動物と、その獲物」という意味があるのだ。料理の世界では大別して「羽のゲーム(雉子、山鳩、ホロホロチョウなども含む)」という鳥の類いと、「毛のゲーム(鹿肉、猪肉、ウサギなど)」に分かれる。鱒などの魚も、それが釣りという競技の獲物という範疇であればゲームに含まれることがある。
カタカナでの使用と、英語での意味がかなり違うシリーズ。まず、ラグーとは言っても、あの瓶に入ってるパスタソースのブランドのことではなく、肉をベースにしたソース全般を指す極一般的なイタリア語なわけで、英語でもそのまま使われるが「パスタソースでしょ?」という人は英語圏にもいるのでまあ、その辺は。それと、今回のテーマで問題なのはgameという英単語である。これは、かなり日本語にならない。一般的にはもちろんスポーツのゲーム、遊戯、競技のようなことを意味するが、gameには「狩猟の対象となる動物と、その獲物」という意味があるのだ。料理の世界では大別して「羽のゲーム(雉子、山鳩、ホロホロチョウなども含む)」という鳥の類いと、「毛のゲーム(鹿肉、猪肉、ウサギなど)」に分かれる。鱒などの魚も、それが釣りという競技の獲物という範疇であればゲームに含まれることがある。
というわけでマーケットやご近所のお肉屋さんでも、比較的簡単に手に入るようになってきたゲーム。今回は野ウサギ丸ごと一匹入手した(というか、丸ごと一匹でしか売ってくれない)。小振りな方らしいが重さにして2.3キロ、臓物もレバーとキドニー(腎臓)くらいは残っている。皮を剥がれたその様は、ナウシカの巨神兵みたいにも見える。そして予想通りだが、匂いがキツい。はっきり言って腐肉の匂いである。挫けずジェイミー・オリヴァーの「Jamie at Home」のレシピとか、複数のレシピを参考に<ラグー>を作ってみる。基本はにんじんとカブカンラン(漢字ではおそらく「蕪甘藍」であろう。イギリス英語ではswedeである)みたいな冬の根菜とタマネギを炒めて、赤ワインで煮る。ジェイミーさんは白ワインを使って軽くしたようだが、先日のボルドーも残ってるし、伝統的なレシピでは赤を使うようだし、今回は赤にした。ひとつ興味深いのはこの、肉の匂いを取るのに加えるのがマーマレードということだ。猪肉にもオレンジピールを入れたが、ゲームにはオレンジの香りがいいのかもしれない。
パスタは、そんなわけで最近気に入っているカサレッチャだが、ニョッキもおいしいかもしれない。ジェイミーのレシピではパッパデッレという幅にして2センチ以上はあろうかという<山梨のほうとう>のようなパスタを使っていた。パスタも自分で作ってみたいんだよなー。
何ぶん、ベルリン出身の友だちが「私みたいな都会育ちにはちょっと」キツ過ぎる光景だと言って目を背けた野ウサギ、妻も「味はいいけど匂いがねえ」と半分も食べなかった野ウサギ。他の調理法も探りを入れてみようと思う。
